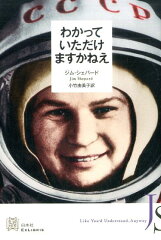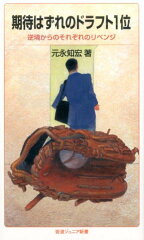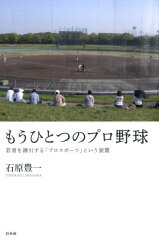ノーベル賞を受賞した大隅教授が、ノーベル賞の賞金、約1億円を利用して基金を作るというニュース。
この数年、ノーベル賞を受賞した日本人研究者が口々に今後が心配、研究環境が劣化しているということを述べていることは気になっていました。こういう基金を作るという動きも大隅教授以外でもあるようです。基金を作って、お金がない学生の研究支援を図るということのようで、これで少しでも研究者の環境がよくなれば、と思います。
が、果たしてそれで済むのだろうか、という思いもあります。
あたしなど研究者を自称してはならないわけですが、一応は大学院を出ています。修士だけですが、世間的には「院卒」です。ドクターへ進んで研究者の道を目指さなかったのか、と問われれば、まるっきり考えなかったということはないですが、ある時点で諦めざる得ませんでした。
あたしは大学から、そのまま大学院へ進んだわけですが、その時点であたしの母校の大学院は修士までしかありませんでした。現在はドクターもありますが、その当時は修士までで、自分が修士在学中に博士課程ができる可能性は低かったです。
ですから、研究者を目指すのであれば、修士を出た後、他大学の大学院に入り直す必要があったわけです。それなら最初から博士課程のある大学院へ進めばよかったのでしょうが、その選択をしなかった時点で、あたしの道は半分くらい決まってしまったと言えるかもしれません。
自分の話が長くなりましたが、研究者支援ということに話を戻すとここからが本題です。大学院の学費は、育英会の奨学金も取れ、また学内の制度で一年目は学費免除の資格を取れたので、なんとかなりました。ニュースを見る限り、この時点の経済的支援がメインであるように聞こえます。
確かに、お金の心配をせずに研究に打ち込めれば安心です。でも、これって、結局はかかるお金を支弁してくれるというだけですよね? あたしの場合、そして多くの人の場合、より問題なのは家族を養わなければならない、生活していかなければならない、ということだと思います。
あたしは大学院一年の時に父が病気を発症し働けなくなりました。有給を消化して早期退職という形になりましたので、あたしが修士二年の時には、すぐにでもあたしが就職して両親を養わなければならない可能性が大いにありました。実際のところ二年生に進級するか中退するかという判断も迫られました。
が、あと一年ということで修士だけは修了しましたが、そこから先、さらに進学するなんて許されない状況でした。特にその数年前に、まだ父が病気を発症する前だったので、ローンを組んで自宅を購入したので、毎月のローンの支払いがありまして、父の年金はほぼそれに消えてしまいました。
そんなわけなので、あたしが働かないとわが家の生活は立ちゆかない状況でした。両親を養う必要がなく、自分だけが暮らしていければ、後は好きなだけ研究に打ち込めるような環境にいる人が果たしてどれだけいるのでしょう?
大学、大学院まで進むと「両親の援助はあてにできない」という話をよく聞きますが、当てにせず自分だけ生活できればよいというのは、あたしに言わせればかなり恵まれた環境です。「親の金を当てにする」のではなく、「親を養う」必要がある立場の人も多いと思うので、そこまでいくと、こういう基金がどこまで助けてくれるのか……
それに、そもそも研究者って、どれくらい研究すれば食べていけるようになるのでしょう? 文系など「大学院は出たけれど……」という人がそこらじゅうにいそうですけど。