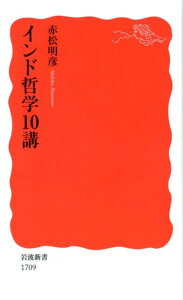5月 2018のアーカイブ
もうじきお目見え!
シーズン到来?
何て言っているのでしょうか? わが同僚ならば問題なし?
今朝の朝日新聞に載っていた記事です。
セシールのCMで、ブランド名の後にモゴモゴと流れるセリフがどのように聞き取られているか、ということです。人間の耳って不思議なものです。
しかし、あたしの勤務先の人々であれば、問題なく聞き取れる人が多数なのでしょうか?
今日の配本(18/05/25)
もう一方の側から見てみると……
今朝の朝日新聞に中朝国境付近で不動産投資ブームという見出しが目に留まりました。
今後の中朝関係の発展を見越して、北京や上海では規制が厳しい不動産投資のマネーを、こういった地方へ注ぎ込んでいる富裕層が多いのでしょう。行く宛のないバブルマネーですね。これが弾けたら、中国経済はどうなってしまうのでしょう?
ところで、記事では不動産投資に熱を上げる漢民族の話になっていますが、この地域は言わずと知れた朝鮮族の居住地でもあります。町によってはほとんどが朝鮮族というところもあるでしょう。中国国内なので朝鮮族と呼ばれますが、つまりは朝鮮人です。歴史的に見れば、このあたりも大朝鮮の領土だった時代もあったわけですから、朝鮮人から見れば、満洲族に追い出されるのならともかく、漢民族にわが物顔に振る舞われるのは忸怩たるものがあるのではないでしょうか。
そんな中国東北地区の様子を朝鮮族の視点からルポしたものが『辺境中国 新疆、チベット、雲南、東北部を行く』です。先日の書評以来注文殺到で、ただいま重版中ですので、しばらくお待ちください。
灯台下暗し
先日、岩波新書の『インド哲学10講』を読んだのですが、その中で野田又夫が引かれていました。
恥ずかしながら、野田又夫って全然知らなくて、ただ引かれている文章などが興味深かったので、著作を調べてみたら手頃なところで岩波文庫の『哲学の三つの伝統 他十二篇』がありました。というわけで、こんどはそれを読み始めたところです。
が、パラパラとページをめくっていた時に、この文庫の底本となった『野田又夫著作集』というのが、あたしの勤務先から出ている本だということを知りました!
えーっ、という感じです。驚きました。なんとなく縁を感じると共に、悔しい思いもいっぱいです。
で、勤務先で少し調べてみると、1981年頃に刊行された全5巻本でした。もちろん現在は品切れです。と言うよりも、そんな本が出ていたということを、今の今まで知りませんでした。あたしが入社したのは著作集刊行から10年ほど後になりますが、周囲に尋ねてみると、どうやらあたしが入社した時点で既に品切れ状態だったようです。
うーん、それでは知らなくても仕方ないですね。しかし、この間、一度も問い合わせすら受けたことなかったというのは、野田又夫というのは知る人ぞ知る学者だったのでしょうか。なにも知らなくて、本当に恥ずかしいです。
しかし、いま読んでいる岩波文庫、非常にわかりやすいですし面白いです。こんな学者がいたんだと、目から鱗です。
大学生になったら? 大学生になるまでに?
くまざわ書店の店頭でフェアをやっていて、その小冊子をいただきました。《大学生になったら読んでおきたい本》フェアです。同チェーン各店で現在開催中なのだと思います。
冊子の最後のページには《くまざわ書店「大学生になったら読んでおきたい本」フェア有志一同》として挨拶文が載っています。有志として本を推薦しているのは同チェーン各店に勤務する書店員10名の方々です。かなり気合いの入った取り組みに感じられます。
内容は「大学生のための読書入門」「大学の内と外をつなげるために」「社会と人間について考えるための本」「心と思想に触れる」「入門 ニッポンを知る」「乱読のすすめ」「立っている足下が崩れる4冊」「自分とは何か、自己を客観的に見る道標になる一冊」「自明性を疑う」「普遍性と特殊性の共犯関係」というテーマで5冊ずつくらい選書されていて、各書籍に選者のコメントが数行付いています。
そんな中、「大学の内と外をつなげるために」の項で『寝るまえ5分の外国語 語学書書評集』を、「自明性を疑う」の項で『ライ麦畑でつかまえて』をそれぞれ選んでいただきました。深謝。
全体で見ると、やはり岩波書店からの選書が目立ちます。その他では筑摩書房、みすず書房などからも多く選書されているなあという印象です。
ところで「大学生になったら」ではなく、「大学生になるまでに」というテーマを設定したらどんな本が選ばれるのでしょうか? 興味あります。
浪漫はかき立てられるけど……
数日前にやっていたTBS系の「浅見光彦シリーズ」は平家の落人伝説をベースとしているストーリーでした。録画されていたのを前半だけ見たのですが、うーん、ヒロインが平家の末裔ということになっていますが、平家の伝説が直接ストーリーに関わってくるのでしょうか? 後半は明日にでもまた見ようと思っています。
さて、あたしは詳しくもなければ調べたこともないですが、日本各地に平家の落人伝説はありますね。今回のドラマの四万十川の上流の山の中の里、そこは平家の落人たちが逃げてきて森を切り開き田畑を開墾し、なんとか生き延びてきたところという設定です。
話の初めが信じるに足のであれば、確かにそこの集落の人は平家所縁の人たちということになりますが、本当のところはどうなのでしょう? 落人ですから、正体を隠さなければならないわけで、一目で平家とわかるような品を所持していれば、集落の中のどこかに隠したはずです。それがいまに伝わっているのか否か……。後から偽造できそうなものだったり、それではとても証拠とは呼べないようなものだったりしたら、もう後は本人たちが信じているということしか残りませんね。まさに信仰と呼ぶべきかも知れません。
しかし、実際のところ、少人数であれば逃げおおせることは可能だったのでしょうか? 当時は戦乱で流民も多数発生したかも知れませんが、基本的に農民主体の日本では、民衆はほとんど生まれ故郷から動かずに一生を過ごしていたのではないかと思います。となると、芸能者的なものや修行僧を除けば、ある程度の集団で移住してくるというのは目立つったらありゃしないでしょうね。だから、人里離れた山奥へ入っていたのでしょうけど……
真面目に考えようとすると、いろいろと矛盾というかおかしなところも散見するのが平家の伝説なのかも知れませんし、義経と同じく、敗れ去ったものにも生き延びて欲しいと願う日本人の心性が、こうした伝説を生んでいるのでしょう。
で、実際に落人たちを見つけたら、近在の農民たちはどうしたのでしょう? 受け入れたのでしょうか? そして仲良く一緒に暮らすようになり混淆が進んだのでしょうか? あるいはお役人に密告されたり、村人たちからは嫌悪され排他的に扱われたのでしょうか?
いろいろ興味は尽きません。
近いのか遠いのか?
あたしの勤務先の最寄り、JRお茶の水駅にある看板です。
「東大寺と東北展」です。東大寺と東北って、あまり関連があるような気はしませんし、共通するのは「東」という漢字だけ、と思いたくなってしまうようなところもあるのですが……
どうやら歴史上、東大寺も何度も災害に遭い、そのたびに復興を果たしてきたということで、東北地方の復興への願いをこめての展覧会のようです。
で、どこでやってるのだろうか、上野かしら、と思ってこの看板をよく見たら、
東京駅より約2時間!!
と書いてあるではないですか! なに、東京じゃないの? だって、お茶の水駅の看板ですよ、てっきり東京のどこかの博物館だと思うじゃないですか。東北歴史博物館ってどこ?
と同館のウェブサイトを見てみると、宮城県の多賀城市にあるようです。うーん、東京駅から2時間。
確かに近いと言えば近いですが、だからといって、ちょっと時間ができたからって「行ってこよう」という距離でも時間でもないですよね?
いや、フットワークの軽い人だったら、「なんだ、近いじゃん」と言って、思い立ったが吉日という感じで訪れてしまうのでしょうか?