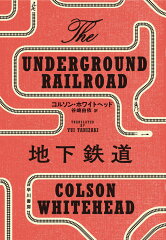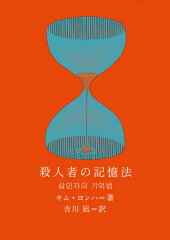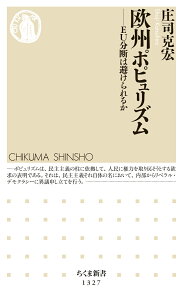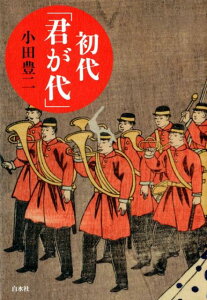本日見本出しの新刊『沸騰インド 超大国をめざす巨象と日本』は現代インドを知るための一冊です。
現代インドに関する本と言えば少し前には『モディが変えるインド 台頭するアジア巨大国家の「静かな革命」』という一冊がありましたが、こちらは「モディ首相を通して現代インドの政治、経済、社会、外交を概観し、南アジアの国際関係を紐解く」一冊で、『沸騰インド』は「政界、経済界のみならず、庶民の生活にも深く分け入った元朝日新聞ニューデリー支局長のルポ」です。併せ読むことでインドを多角的、多面的に知ることができるはずです。
さらにインドについてという方にはこんな本は如何でしょうか? 『パール判事 東京裁判批判と絶対平和主義』『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』『インド独立の志士「朝子」』、インドの歴史を知るための三冊です。
インドの神話を大胆にアレンジした『マナス』も、インドの別な一面を見せてくれます。『インド通』は70回以上の渡印歴を誇る著者のフィールドワークです。
『ビルマ・ハイウェイ 中国とインドをつなぐ十字路』はインドと中郷に挟まれたミャンマーの地政学、『アジア再興 帝国主義に挑んだ志士たち』は、三人の主人公一人はタゴールです。
最後にインドの言葉を学びたい方には以下をお薦めします。
『ニューエクスプレス ヒンディー語』『ニューエクスプレス ウルドゥー語』『ニューエクスプレス タミル語』『ニューエクスプレス ベンガル語』を出しております。ビジネスの世界では英語なのかも知れませんが、現地の言葉を少しでも話せると、お互いの距離がグッと縮まるはずです。