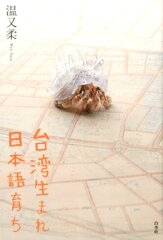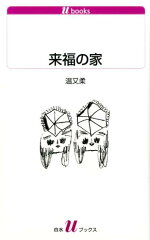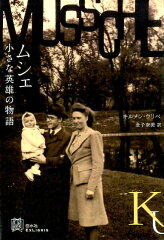11月9日に乃木坂46のニューシングル(16枚目)が発売されるというのに、いまだタイトルも選抜メンバーも発表されていないということで、ファンの間ではやきもきとした空気がかなり濃厚に漂っています(笑)。
そこまで追いかけているわけではないので「いつもなら」ということは言えませんが、それでも発売の一か月前には歌番組や冠番組などでの披露というが一般的だったように思います。「ああ、こういう曲なんだ、結構いいんじゃない」と思ってもらい、そして購買に結びつける、というのが自然な流れではないでしょうか?
が、既に一か月前だというのに、握手会などのスケジュールは発表され、初回特典などもアナウンスされているというのに、肝心の曲がどうなるのか、そしてファンにとってはそれなりの関心事である選抜メンバーがどうなるのか、誰がセンターなのか、といったことがまるっきり霧の中です。
いや、あたしはそこまで熱くなっているわけではありません。気にならなくはないですが、誰が選ばれても、誰がセンターでも、そしてどんな曲であってもCDを買うことに変わりはないのですから……(汗)
ただ、ファンサイトでのヲタたちの発言を見ていてちょっと不思議に思った、と言いますか、思い出したことがあります。
それは、日本のアイドル歌手の場合、シングルが発売され、そのシングルが何枚かたまったらアルバムを出すという流れが主流だということ、それに対して欧米の歌手の場合、まずアルバムを出し、そこからシングルカットされていくという流れが一般的であるという、その違いです。
いえ、別にすべての歌手がそうであると断言できるほどの材料を持ち合わせているわけではありません。ただ、あたしが(CDなんかまだなかったので)レコードを買うようになった中学、高校のころは、松田聖子や中森明菜がデビューしたころで、こういったアイドル歌手はシングル先行で、それらを収録したアルバムが後から出るのが普通だったと記憶しています。それに対して、当時は洋楽が人気を博した80年代ですが、そのころ流行っていた洋楽のスターたちはまずアルバムを出し、そこからシングルカットをしていったと記憶しています。
中学生や高校生ですから子供心にという表現はふさわしくありませんが、とにかく日米(アメリカだけでなくイギリスも含む)のレコードの発売の仕方の違いに新鮮な驚きを覚えたものです。
ということで、話は戻って乃木坂46です。

乃木坂46は「透明な色」「それぞれの椅子」という二枚のアルバムを既に出しています。ファーストアルバム「透明な色」はそれまでのベスト盤的な性格の濃いものでしたが、それでも新曲が何曲か含まれています。そしてセカンドアルバム「それぞれの椅子」も、ファースト以降のベスト盤的な構成ではありますが、やはり新曲が入っています。
その中の一曲「きっかけ」はファンの間でも名曲と評価が高く、アルバム発売直後の歌番組でもしばしばこの曲が披露されたこともあるくらいです。またミスチルの桜井がこの曲を気に入り、コンサートで歌ったということも話題になりました。
なので、あたし的には「16枚目はどんな曲?」と焦らされるくらいなら、先行するアルバムからのシングルカットでもよくはないか、そう思うのですが……