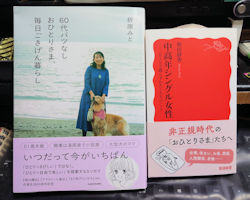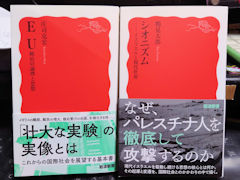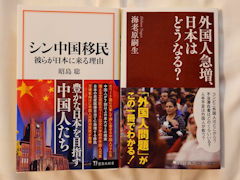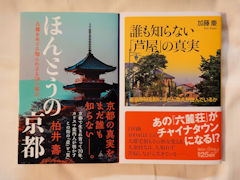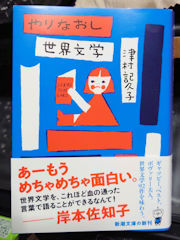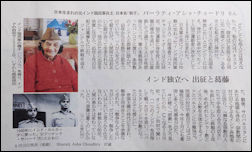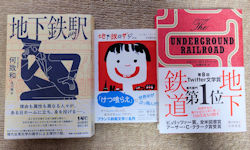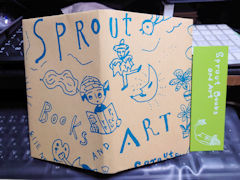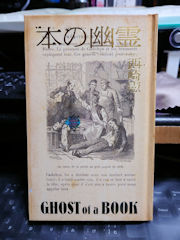中公新書から『昭和天皇』が発売されました。かつて同タイトルのものが発売されていましたが、今回のはその「増補版」で、著者も変わりません。
 中公新書ではこれまでも「増補版」が刊行になるタイトルがありまして、わが家の書架を見てみますと『南京事件』と『キメラ』が「増補版」を刊行しています。
中公新書ではこれまでも「増補版」が刊行になるタイトルがありまして、わが家の書架を見てみますと『南京事件』と『キメラ』が「増補版」を刊行しています。
まずは『南京事件』をご覧ください。中公親書しての通し番号は旧版も増補版も同じ795です。増補版が刊行されたら旧版は絶版とし、新旧で入れ替えてくださいということなのでしょう。
そして『キメラ』の方も通し番号はどちらも同じ1138です。こちらも新旧の入れ替えを推奨しているようです。
 ちなみに一つの本につき一つ割り振られるISBNコードというのがありまして、『南京事件』の旧版は「4-12-100795-6」、増補版は「978-4-12-190795-0」と一つ異なるところがあります。ISBNコードが10桁から13桁に変わったのはひとまず無視します。
ちなみに一つの本につき一つ割り振られるISBNコードというのがありまして、『南京事件』の旧版は「4-12-100795-6」、増補版は「978-4-12-190795-0」と一つ異なるところがあります。ISBNコードが10桁から13桁に変わったのはひとまず無視します。
『キメラ』も旧版「4-12-101138-4」ですが、増補版は「4-12-191138-5」となっていて、『南京事件』と同じ箇所が同じように異なっています。中公新書では、増補版は「9」を振るのが通例のようです。
 ところがこのたび発売された『昭和天皇』は旧版は2105ですが、増補版は2888と新しい番号が振られています。通し番号が異なりますので、ISBNコードも旧版は「978-4-12-102105-2」なのに対して、増補版は「978-4-12-102888-4」と全く異なるものになっています。
ところがこのたび発売された『昭和天皇』は旧版は2105ですが、増補版は2888と新しい番号が振られています。通し番号が異なりますので、ISBNコードも旧版は「978-4-12-102105-2」なのに対して、増補版は「978-4-12-102888-4」と全く異なるものになっています。
「増補版」は同じ通し番号を使うという原則(法則?)が崩れています。これは編集部内で方針が変わったのでしょうか。それとも昭和天皇に敬意を表した措置なのでしょうか。いや、増補版で通し番号を変えるのが敬意を表わしたことになるのかわかりませんが……
あたしはこの三点以外の中公新書がどうなっているのかわからないので、これ以上はなんとも言えませんが、たまたま今回の新刊で気づいたのでちょっと書き留めてみました。
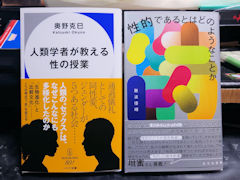 一つはハヤカワ新書の『人類学者が教える性の授業』、もう一つが光文社新書の『性的であるとはどのようなことか』です。どちらも下ネタではなく、極めて真面目な内容の本であることは言うまでもありません。
一つはハヤカワ新書の『人類学者が教える性の授業』、もう一つが光文社新書の『性的であるとはどのようなことか』です。どちらも下ネタではなく、極めて真面目な内容の本であることは言うまでもありません。