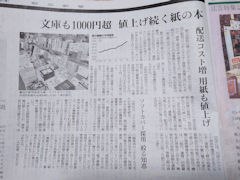書店店頭でミニフェアをやっていて、こんなチラシが置いてありました。
 なんとなく閉塞感の漂う現代社会にピッタリの企画ですね。ハッシュタグは「社会運動の現在形」となっています。SNSで検索すれば、いろいろヒットするのでしょうか?
なんとなく閉塞感の漂う現代社会にピッタリの企画ですね。ハッシュタグは「社会運動の現在形」となっています。SNSで検索すれば、いろいろヒットするのでしょうか?
チラシを広げてみますと、
そういえば、知ってたら協力できたのに…と思ったことはありましたよね。
そういえば、理不尽なこと、耐え続けてる人いますよね。
そういえば、非暴力で戦ってる人、いますよね。
そういえば、民主主義って ことば ありましたよね。
という惹句が踊っています。これだけを見ると、あたしの勤務先から刊行している書籍も一緒に並べてほしいなあと思ってしまいますが、このフェアはその書店の方が企画したものなのでしょうか? それともどこかの出版社が企画したフェアなのでしょうか?
このチラシには主催者とか問い合わせ先、発行元が書いてありませんが、多くの書店でやっているフェアなのでしょうか?