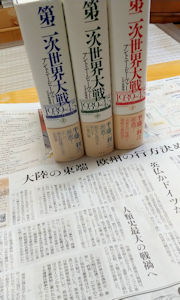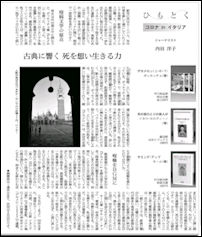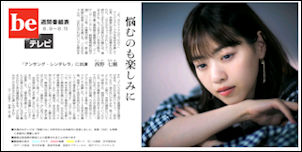関西テレビ系の番組「セブンルール」、今週と来週は本屋さん特集だそうで、一回目の今回、取り上げられたのは大阪の隆祥館書店でした。業界では有名な書店ですね。放送をご覧になれなかった方もご覧になった方も『13坪の本屋の奇跡
』のご一読を!
二村さんのセブンルールはともかく、「街の本屋」という拘りが好きです。やはり何度もセレクト型書店にしてみたらと言われたんですね。それでも頑なに街の本屋であり続けるところに矜持を感じます。
13坪しかありませんから、何を置くというよりも何を置かないかが肝心のようです。数年前に大阪で行なわれた商談会の時に、わざわざあたしの勤務先のブースに足を運んでくださり、お店に置いてみたいと言ってくださいました。それ以来、新刊案内を送るようになりました。
番組に映った限りでは、あたしの勤務先の書籍は見つけられませんでしたが、お客さんに勧めたくなるような本を作っていかなければと思いながら視聴しました。それにしても、大阪という周辺にそれなりに人口のある立地、そして自社ビルだからこそ続けられている面はあると思います。しかし、逆に考えれば、周辺人口もあり自社ビルであれば、本屋なんか辞めちゃってテナントとして貸した方がはるかに儲かるし楽だろうと思います。たぶん、そういう声も数え切れないくらいかけられているのではないでしょうか。でも父の言葉を守ってやれる限り街の本屋を続けていくのだろうなあと思いました。
ところで、どの書店にも二村さんのような書店員がいれば本屋って続けていけるものなのでしょうか?