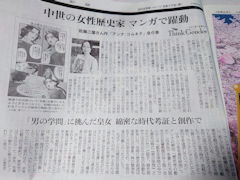土曜日と言えば、新聞の読書欄が気になるというのはこの業界の恒例です。日曜日に載る新聞もありますが……。そして先々週の『陽だまりの昭和』、先週の『日本の反戦非戦の系譜』に続き、今週はこちらの書籍が掲載されています。
 それが『厨房から見たロシア』です。著者はヴィトルト・シャブウォフスキ。あたしの勤務先からこれまでに『踊る熊たち』『独裁者の料理人』を刊行しています。どちらも話題となり、好評をもって受け入れられた二冊です。
それが『厨房から見たロシア』です。著者はヴィトルト・シャブウォフスキ。あたしの勤務先からこれまでに『踊る熊たち』『独裁者の料理人』を刊行しています。どちらも話題となり、好評をもって受け入れられた二冊です。
そして本日の評を読むと、これもまた面白そうな一冊ですね。自社の本なのに読んでいないのが、営業としては申し訳ないのですが、改めて面白そうな本だと認識した次第です。ちなみに本書もそうなのですが、『独裁者の料理人』もレシピが掲載されていますので、日本でどれだけ食材や調味料が揃うのかわかりませんが、ご興味がある方は挑戦するのもよいのではないでしょうか?
 ところで二枚目の画像は、本日の読書欄を引きで撮った写真です。写っている書籍をご覧になって気づかれた方はいらっしゃるでしょうか。
ところで二枚目の画像は、本日の読書欄を引きで撮った写真です。写っている書籍をご覧になって気づかれた方はいらっしゃるでしょうか。
とはいえ、何に気づけばよいのか、気づく点はいろいろとありますよね。申し訳ありません。実はここに写っている出版社に注目してほしいのです。
東京大学出版会、みすず書房との三社で、四年に一度「レビュー合戦」というフェアをやっていますが、その三社が勢揃いしているのです。「レビュー合戦」は三社の社員がそれぞれ他社の書籍をお互いに批評し合うというフェアで、オリンピックイヤーに書店で開催しているものですが、いみじくも朝日新聞紙上でレビュー合戦っぽいものが再現されてしまったわけです。