日向坂46のメンバーが、22名中18名も新型コロナウイルスに感染してしまったというニュース、その前には乃木坂46でも多くのメンバーが感染していましたね。
どちらのニュースにも共通しているのは、体調不良で念のためPCR検査を受けたら陽性だったというものです。乃木坂、日向坂に限らず芸能人、著名人がコロナ感染を報告するときは、ほぼ異口同音に体調不良で検査をしてみたら、となっています。
この体調不良というのは、どういうものなのでしょう?

 発熱でしょうか? それとも倦怠感? あるいは関節などの痛み? 喉の違和感? たぶん人によって症状の出方は様々なのでしょう。そして、ああいう仕事をしているからでしょう、それらの症状が出たら、すぐにPCR検査を受けてみるという体勢になっているのだと思います。
発熱でしょうか? それとも倦怠感? あるいは関節などの痛み? 喉の違和感? たぶん人によって症状の出方は様々なのでしょう。そして、ああいう仕事をしているからでしょう、それらの症状が出たら、すぐにPCR検査を受けてみるという体勢になっているのだと思います。
しかし、一般的に体調不良なんて誰にでも、それもしょっちゅうあるものではないでしょうか? 冬の時季であれば風邪の諸症状はコロナと共通するものが多いですし、更には春先の花粉症も似ています。風邪なのか花粉なのか、よくわからないと言いながら、この数年はそこにコロナが加わっているような感じです。

 あたしは、もうここ何年も、たぶん十数年、あるいは数十年だと思いますが、寝込むような体調不良になったことはありません。基本は健康なのです。ただ、そのぶんちょっと体調が悪いなあ、と感じることはしょっちゅうありまして、頭痛などはもう慢性化していて、数日おきにロキソニンやバファリンを飲んでいます。その他にも、自宅にはイブクイックやセデスなど複数の鎮痛剤を常備していますし、通勤カバンにも何粒か持ち歩いています。
あたしは、もうここ何年も、たぶん十数年、あるいは数十年だと思いますが、寝込むような体調不良になったことはありません。基本は健康なのです。ただ、そのぶんちょっと体調が悪いなあ、と感じることはしょっちゅうありまして、頭痛などはもう慢性化していて、数日おきにロキソニンやバファリンを飲んでいます。その他にも、自宅にはイブクイックやセデスなど複数の鎮痛剤を常備していますし、通勤カバンにも何粒か持ち歩いています。
あたしと頭痛との付き合いはもう数十年になりまして、慣れっこなのでさほど気にしていませんが、同じように長い付き合いの症状に腹痛があります。腹痛と言うよりは腹下しと言った方が正確です。

 これも小さいころからお腹の弱い子供だったので、下痢止め(止瀉薬)にはずーっとお世話になっていますが、大人になってからは専ら正露丸です。あの匂いがダメという人も多いですが、あたしは慣れてしまったので何も感じません。臭いなどと思ったことすらありません。
これも小さいころからお腹の弱い子供だったので、下痢止め(止瀉薬)にはずーっとお世話になっていますが、大人になってからは専ら正露丸です。あの匂いがダメという人も多いですが、あたしは慣れてしまったので何も感じません。臭いなどと思ったことすらありません。
この腹痛、以前は時々襲ってくる程度でした。それこそ夏にちょっと冷たいものを食べすぎたとか、緊張から来るストレスなど、わかりやすい原因が多かったのですが、この数年はちょっと異なります。
この数年、たぶんもう五年くらいになると思いますが、食事をするとお腹を壊してしまうのです。朝は軽くしか食べないのでまだよいですが、夕飯後はほぼ毎日お腹を下します。別に変なものを食べたわけでもなければ、必要以上に食べ過ぎているわけでもありません。食事を終えるとじきにお腹がキュルキュルしてくるのです。
なので、ここ数年、仕事に出ているときは昼食は食べていません。昼休みなしで働いています。だって、食べるとお腹が気になってしまいますから。自宅で食べる夕食後は寝る前に何度かトイレに行くこともしばしばで、ここで登場するのが正露丸です。
これが目下の体調不良です。ちなみに、あたしは正露丸が日露戦争の時の腹痛対策で作られた薬で、本来は「征露」だったということは、当然知っております。
 今朝の朝日新聞には、あたしの勤務先に縁のある方の訃報が2件も載っていました。
今朝の朝日新聞には、あたしの勤務先に縁のある方の訃報が2件も載っていました。 続いては、菊地信義さん。菊地さんは有名ですからご存じの方も多いでしょう。朝日新聞の記事では『装丁談義』の名前が挙げられていますが、あたしの勤務先からは『新・装丁談義』を出しています。
続いては、菊地信義さん。菊地さんは有名ですからご存じの方も多いでしょう。朝日新聞の記事では『装丁談義』の名前が挙げられていますが、あたしの勤務先からは『新・装丁談義』を出しています。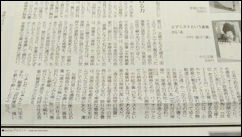 そして最後は、在庫僅少どころではなく、品切れの本が今日の読書欄で紹介されていました。『遠方より無へ』です。
そして最後は、在庫僅少どころではなく、品切れの本が今日の読書欄で紹介されていました。『遠方より無へ』です。![オーケストラの音楽史[新装版] 大作曲家が追い求めた理想の音楽](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560094322&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)


















