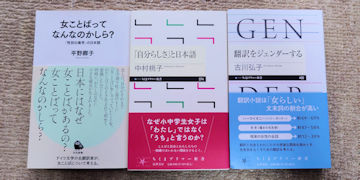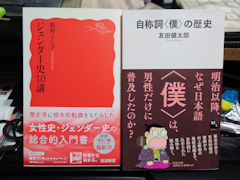衆議院議員選挙の本日、朝日新聞には本にまつわるこんな記事が載っていましたので、ご紹介します。
商店街に自由に本を持ち寄り、持って行っても構わない施設があるそうです。思い出してみますと、わが家の最寄り駅の一つ、JR中央線の武蔵小金井駅にも似たようなものがありました。
改札内の通路に木製の本棚が一つ置いてあって、読み終わった本、要らない本を持って来て自由に置いていってよかったのです。そして、そこに置いてある本は誰でもが自由に持って行って構わないことになっていました。もちろん本を置く、本をもらっていく、どちらもお金はかかりませんし、誰かが本の状態や内容をチェックしているわけでもありませんでした。
 こういう施設、今もあったらよいと思うのですが、中央線の高架化工事で駅舎の建て替え工事が始まると共になくなってしまい、工事が終わってからも復活はしていません。残念なことです。
こういう施設、今もあったらよいと思うのですが、中央線の高架化工事で駅舎の建て替え工事が始まると共になくなってしまい、工事が終わってからも復活はしていません。残念なことです。
続きまして、社会面に載っていた記事。塀の中と外の読書会のお話です。
刑務所内でも読書会が行なわれているのですね。受刑者はよく本を読むようですので、こういう取り組みは受刑者にとってもよいのではないでしょうか。本のもつ力を感じさせるエピソードだと思います。