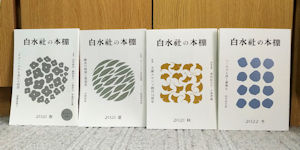ネットニュースで知ったのですが、本日2月6日は英国のエリザベス女王即位の日だそうです。今日で即位70年になるそうです。
ネットニュースで知ったのですが、本日2月6日は英国のエリザベス女王即位の日だそうです。今日で即位70年になるそうです。

ある日、愛犬を追って城の裏庭にやってきた女王陛下は、移動図書館の車と、本を借りにきていた厨房の下働きの少年に出くわす。あくまでも礼儀上、一冊借りたことが、人生を変える、本の世界への入り口となった。以来、すっかり読書の面白さにはまってしまい、カンニングする学生のように公務中に本を読みふけるわ、誰彼かまわず「最近どんな本を読んでいますか」と聞いてはお薦め本を押しつけるわで、側近も閣僚も大慌て。読書によって想像力が豊かになった女王は、他人の気持ちや立場を思いやるようになるものの、周囲には理解されず、逆に読書に対してさまざまな妨害工作をされてしまう……。

さて、エリザベス女王は英国における究極の上流ですが、英国の上流階級に興味をお持ちの方には、現在売行き絶好調のこちら、『ノブレス・オブリージュ イギリスの上流階級』がお薦めです。
ドラマ「ダウントン・アビー」やジェイン・オースティンの小説が好きな方であれば、こちらも大いに楽しめるはずです。是非手に取ってみてください。