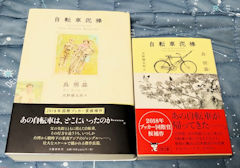オビだけを読むと戦争をテーマにした重苦しい作品なのかなという印象を受けるかも知れませんが、そんなことはありません。もちろん台湾から日本にやってきた少年工たちの戦争との関わり方が描かれていますので、戦争が大きな背景になっていることは確かです。ただ、そこには暗さとか重さといったものは、少なくともあたしには感じられませんでした。もしかすると、これが呉明益世代の台湾人にとっての戦争との距離感なのかも知れません、
そして、今回は日本の読者に対して大いにアピールしたいのは、本作に出てくる日本人青年の平岡君です。彼については本作の公式サイトにも内容紹介で以下のように触れられています。
三郎が暮らした海軍工廠の宿舎には、勤労動員された平岡君(三島由紀夫)もいて、三郎たちにギリシア神話や自作の物語を話して聞かせるなど兄のように慕われていたが、やがて彼らは玉音放送を聴くことになるのだった――。
そうです、平岡君とは後の三島由紀夫のことなのです。

さらに原作者・呉明益さんも『我的日本 台湾作家が旅した日本』所収の「金魚に命を乞う戦争――私の小説の中の第二次世界大戦に関するいくつかのこと」で三島由紀夫と高座について書かれています。是非、こちらも読んでいただければ幸いです。
なお呉明益さんは10月下旬に河出書房新社から『雨の島』という新刊が刊行になりますので、そちらも是非お楽しみに。