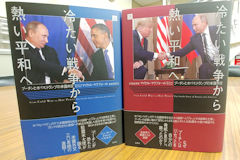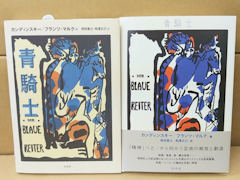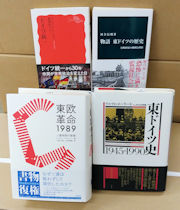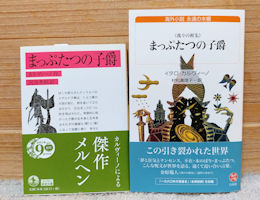同じタイトルの本というのが、時々あるものですが、最近こんな書籍を発見しました。
中央公論新社の新刊『クルスクの戦い 1943 第二次世界大戦最大の会戦』です。そしてもう一冊が、あたしの勤務先の『クルスクの戦い1943 独ソ「史上最大の戦車戦」の実相
』です。
副題こそ異なりますが、正題は共に「クルスクの戦い1943」です。著訳者は前者がローマン・テッペル著、大木毅訳で、後者はデニス・ショウォルター著、松本幸重訳です。四六判で400ペイジを超える分量はどちらも同じです。
公式サイトによる内容紹介は、前者が
独ソ戦の研究の最前線。第二次世界大戦の帰趨を決した戦いの一つ、クルスクの戦いをドイツ、ロシア両国の資料から精緻に分析し、著しく歪曲されてきたそのイメージを刷新する。
で、後者は
「ツィタデレ作戦」の背景、準備、戦闘の経過、圧巻のプロホロフカの戦車遭遇戦、作戦の挫折を、米国の長老軍事史家が新資料を駆使して精緻に描写。地図・口絵・索引収録。
です。同じ素材に関する書籍ですから煮てしまうのは仕方ないですが、書店店頭や読者が迷ったり、間違えた発注が起きないか、そこがちょっと心配です。