 小説『フランス組曲』がこのたび新装版として生まれ変わりました。
小説『フランス組曲』がこのたび新装版として生まれ変わりました。
いかがでしょうか?
どちらの方がお好みですか、と聞いても旧版はもうございませんのでスミマセン。
これからは右側の新装版でお楽しみください。
日々の営業活動に関するあれこれ
夏前のWEB書店商談会の第二弾として先週から秋の書店商談会が始まっています。前回は、社としては数社の商談がありましたが、あたし自身は一店舗としか商談はできませんでした。
今回は違います。こちらからも積極的に声をかけ、あたし個人でも4件の商談を行ないます。
さて、ZOOMには背景という機能があります。何も設定しないと、PCのカメラが写す自分自身と、その背後の風景が映り込むわけです。勤務先でやっていますと、WEB商談用のスペースなどないので、自分のデスクでやることになるわけですが、そうなるとオフィスが丸映りです。別に映って困るようなものがあるわけではありませんが、今どきのカッコイイ洗練されたオフィスならまだしも、雑然としているので映ってしまうのはどんなものかという気もします。
 映り込む映像、社内の風景はまだよいのですが、立ち働いている同僚まで映ってしまうのは、なんか商談に集中できないのではないかと思っています。あたしではなく、相手が、ですけど。もちろん、映り込む風景よりも電話などの音、商談の場に置いては騒音にしかならない音は如何ともしがたいです。
映り込む映像、社内の風景はまだよいのですが、立ち働いている同僚まで映ってしまうのは、なんか商談に集中できないのではないかと思っています。あたしではなく、相手が、ですけど。もちろん、映り込む風景よりも電話などの音、商談の場に置いては騒音にしかならない音は如何ともしがたいです。
というわけで、音に関しては自宅で商談した方がまだ静かなんですよね、あたしの場合は。
で、前回の商談会では自宅から参加し、その時はあたしの部屋の一部が映っていたわけです。勤務先以上に、見られて困るものなど置いていないので、全然構いませんが、生活感があふれすぎてしまっていたかも知れません。
ところで、ネットを調べていましたら、背景に名刺を設定することができるということを知りました。いわゆる、オンラインでの商談が増え、そうなると名刺交換はどうなるんだ、という声に応えてさまざまなサービスがリリースされているようです。
そんな中から、無料で自作で消える名刺は医系サービスを使って作ったのが、画像のものです。あたしが、もう十数年前に訪中した折に、西安の兵馬俑で撮った写真を使っています。ここに名刺の要素とSNSなどにリンクしたQRコードが配置されているものです。
こんな背景だと、かえって商談に差し障りが出てしまうでしょうか? でも、とりあえずお初の方にも必要な情報は提供できているかと思うのですが……
 筑摩書房の新刊『中東全史 イスラーム世界の二千年
筑摩書房の新刊『中東全史 イスラーム世界の二千年』を手に入れて思い出したのが、こちらの上下本『アラブ500年史 オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで
』です。
500年と2000年。ちくま学芸文庫の方が網羅している歴史が長いですが、やはり視点も異なりますし、興味ある方はどちらも読むことになるのでしょうね。
ちなみに『500年史』の方はサブタイトルにあるようにオスマン帝国以降の500年を扱っていまして、オスマン帝国については、同著者による『オスマン帝国の崩壊 中東における第一次世界大戦』という本も刊行されていますので、この地域の歴史に興味がある方には、やはり必読の文献でしょう。
 ところで、筑摩書房ですが、実は同時期に新書で『中東政治入門
ところで、筑摩書房ですが、実は同時期に新書で『中東政治入門』なんていう一冊を刊行しているんですよね。いきなりの中東ブーム(?)、いったいどうしてしまったのでしょう?
まあ、中東情勢は日本にとってはやや縁遠いものがありますが、常に国際政治の注目を集めている地域ですから、日本でももっと関心を持たれてもよいはずですし、関連書籍がもっと売れてもよいはず何ですけどね。
特に、アルカイダやイスラムといった紛争をメインに扱ったものではなく、客観的な歴史、もっと地域全体を俯瞰できるような書籍が増えてくるといいなあと思います。いや、あたしが知らないだけで、日本でもそれなりに出ているのかもしれませんが。
そう言えば、文庫クセジュに『近東の地政学 イスラエル、パレスチナ、近隣のアラブ諸国』なんていう一冊もありました。
あたしの勤務先も徐々にコロナ以前の状態に戻りつつあります。現在は、営業部の場合、ほぼ全員、週に二日の在宅勤務日を設けて、社内の密を避けるようにしています。が、これも徐々に緩和の方針。もちろん、無理に出社しろというのではないですが、時短勤務も今月後半からは解除になります。
自宅に幼児やお年寄りが同居している人の場合、確かに自分が外へ出かけていることでウイルスを持ち帰ってしまう可能性があり、そこから家庭内感染に至るリスクは避けたいものです。社員の家庭環境は一律ではないので、柔軟な対応も必要になってくるでしょう。
さて、あたしです。
現在は週に二日在宅していますが、来週くらいからは週に一日、様子を見ながら在宅なしに移行していこうと思っています。そして書店回りも少しずつ再開します。外回りに出てしまえば、社内の密と言うことに関しては避けられます。在宅と同じ効果です。もちろん、書店回りということは電車の中など不特定多数の人と接する機会が増えるわけなので感染リスクは高まりますが、現在の日本でそれを気にしていたら全く動けなくなってしまいます。自分なりの予防対策をした上で働くしかないようです。
それに加えて、それなりに元気ではありますが、わが家には七十代後半の母が同居していますので、呼吸器系の疾患はありませんが、年が年ですから感染してしまったらと思うと、やはりちょっと怖いです。
で、話は戻って、あたしの勤務時間です。
週二日の在宅日以外、つまり出社する日については通勤電車のラッシュを避けるため、朝早くに自宅を出ています。たぶん以前にも書きましたが、朝4時半には家を出て、バスもまだ始発前なので約30分駅まで歩いています。この季節は外はまだ真っ暗です。徐々に寒くもなってきました。
勤務先には6時前に到着します。一応、公式には7時からの勤務ということになっていて、現在は6時間の時短勤務なので、昼休みを取らず13時まで仕事をしたら帰宅という日々です。もちろん、2時半ころに自宅に到着しても、なんだかんだメールは入ってくるので、午後5時までは自宅のパソコンの前で仕事らしきことをしています。
こんな生活ですと、書店回りを復活した場合、勤務時間が恐ろしく長いことになります。なので以前のような出勤時間に、とりあえずは戻すことを検討中です。コロナ以前は7時出社でした。ただ、自宅から駅までのバスが走っている時間になるので、朝の30分の徒歩はなくなりますので、朝2時半に起きるような必要もなくなります(汗)。30分の徒歩は、コロナ下の貴重な運動ではありましたが、それもそろそろ終わりになりますね。
で、夕方のラッシュを避けるために午後は3時過ぎから4時くらいまで書店回りをして帰路に着く、という感じになりそうです。もちろん書店回りは相手のあることですので、こちらの都合通りにはならない場合もあるでしょうが。
それにしても、朝4時半に家を出るために、この半年、朝は2時半に起床していたのですが、そうなると、前の晩は8時頃には寝ないと寝不足になります。いや、もう夜は7時を回ると眠たくなってきます。体が睡眠を欲しています。でもコロナ以前に戻れば、この生活が2時間くらいはずらせるようになるでしょう。
今週からZOOmを使った書店WEB商談会が始まりました。あたしも今後、商談会に参加する予定ですし、あたしの勤務先としても何件か予約が入っています。
この商談会、ZOOMを使ってやるので、パソコンやスマホ、タブレットとネットワーク環境があればどこででもできるわけで、書店の方はお店の事務所から参加されることが多いようです。書店の場合、一人一台パソコンがあるわけではないようなので、事務所に置いてある共用パソコンを一時的に使うことになるみたいです。なかなか参加出来る時間にも制約が出て来そうです。
一方の出版社側ですが、多くの社で一人一台のパソコン環境になっていると思われるので、参加のハードルは低いです。ただし、ゆっくりと静かに書店の方と話(商談)ができる環境があるかと言えばちょっと疑問です。
あたしの勤務先、別にあたしのデスクの周りに映ってはいけないものがある、ということはないのですが、営業部なのでしょっちゅう電話が鳴りますし、お客さんが見えたりします。商談中のあたしには関係ありませんが、電話や来客に対応する同僚の声がちょっとうるさく感じられるかも知れません。
となると自宅から。実は、社内のZOOM会議などに自宅から参加したことがあります。一応、学生時代以来の勉強部屋がそのままあり、そこにパソコンなどを置いていますが、周囲は本棚だらけです。PCチェアに座ると、後ろにはちょうど中華書局の「二十四史」が並んでいる書棚が見え隠れしています。
背景が本棚なんて、出版社の人間としては申し分の無い背景になると思うのですが、いかがでしょうか?
ということで、本日は『月 人との豊かなかかわりの歴史』をお薦めいたします。
月に関する本は、写真集をはじめ多くあると思いますが、こういった文化史的な書籍は少ないのではないでしょうか? 今日みたいな日には、是非とも本書を手に取っていただきたいものです。
書店員の皆さん、図書館員の皆さん、在庫をお持ちであれば、ちょっと面陳していただけませんか?
そうそう、月と言えば、寒山寺ですね!
朝出社すると勤務先の複合機にファクスがたくさん届いています。
複合機なのでパソコンのプリンター(カラー)でもあり、ファクシミリでもあり、スキャナーとしても使える機種です。なので相当酷使していると思います。
そんな複合機の機能の一つに、届いたファクスをクラウド上にアップロードする機能があり、これまでは使うことのなかった機能ですが、在宅ワークが始まった春先から使うようになりました。
自宅からクラウドへアクセスし、複合機に届いたファクスを確認できるのは非常に便利です。ファイル名は文字の羅列ですから、一覧表示だとどこから届いたファクスなのかはわかりませんが、届いたファクスを一枚一枚確認する作業という意味では同じことなので、それほど苦にはなりません。
担当の書店からのファクスで、返事をしなければならないものとか、自宅からでも確認できるのは便利ですし、いかにもテレワークをしている実感が持てる瞬間でもあります。注文のファクスとか返品了解のファクスとか、本当なら自宅から処理してしまいたいところです。
いや、やろうと思えばできないこともないのですが、問題がいくつかあります。
注文ファクスの場合、出社している人が在宅ワーク中の人の分も処理するのがルールとなっています。これはどの職場でも同じようなものでしょう。となると、あたしが自宅から処理してしまうと、二重処理(二重発注・二重受注)のようなことになってしまい、かえって出社している人の手間を増やしてしまう可能性があります。
クラウドで確認できると同時に、ファクスは紙で出力もされていますので、これはどうしても避けられない事態です。紙の出力を止めるということも可能ですが、そうなると誰がすべてのファクスを確認するのでしょう? 見落としだって起きかねません。全員が在宅ワークになって、ファックスは紙で出力しないとなれば、それに合わせたルールができるのでしょうけど、あたしの勤務先のように在宅が3分の1くらい、残りは出社という体制ですと、なかなか難しいところです。
 本日、9月21日は、ショーペンハウアーの没後160年になります。
本日、9月21日は、ショーペンハウアーの没後160年になります。
学生時代に図書館で蔵書目録を調べるときは「ショーペンハウアー」以外に、「ショウペンハウアー」「ショウペンハウエル」と言った呼び方、読み方でも検索しないといけなかったのを思い出します。最近のネットですと、「ショーペンハウアー」だけで検索しても他の二つの検索結果まで表示してくれるものが多いので非常に助かります。
そんなショーペンハウアー、あたしも勤務先から刊行されている全集、ずいぶん前に購入しておりまして、ご覧のようにわが書架の一画に鎮座しております。輸送ケースのまま置いてあり、全集の上には線装本、右側と左側には中国古典が並んでいるところなど、いかにもあたしの書架という感じが濃厚に現われています(汗)。
年とって、退職したら、のんびりと読むとしますかね……(笑)
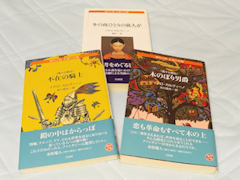 本日、9月19日はイタロ・カルヴィーノの没後35年にあたります。
本日、9月19日はイタロ・カルヴィーノの没後35年にあたります。
あたしの勤務先からは『冬の夜ひとりの旅人が』、そして《我々の祖先》三部作の『不在の騎士
』『木のぼり男爵
』が刊行されています。《我々の祖先》三部作の三つめ、『まっぷたつの子爵』は新訳で10月下旬刊行予定です。旧訳は「岩波文庫
」から出ています。
その他にも、カルヴィーノは各社から翻訳が出ていますので、ご興味がある方はぜひ本屋で探してみてください。
9月になりました。
考えてみると、もう半年近く書店営業に行っていません。他の出版社はどうなのでしょう? 都心部の大型店などは顔を出している出版社もあるみたいですが、全体的にはかつてのような沿線をこまめに回って歩くような営業は影を潜めているようです。
それが出版社の売り上げにどういう影響を及ぼしているのか、営業スタイルは今後どうなるのか、ということも気になりますし、真剣に考え、取り組まなければいけない課題ではありますが、それよりも気になるのは書店の現場です。やはり読者や、その読者と直接接する書店がどうしたいか、どうして欲しいかによって出版社の営業も変わってくると思うので。
単純に考えると、出版社の営業がぱったり来なくなって、書店の方は営業マンとの商談・雑談に取られていた時間が解放されるので、棚のメンテやお客様対応に十分な時間が取れるようになったのではないかと思います。「アポも取らずに突然忙しいときにやって来て……」と言われることの多い出版社営業がほとんど来なくなったのですから、書店現場としては万々歳なのではないでしょうか?
一方、営業マンからいろいろと貴重な情報をもらっていたのがなくなってしまって(減ってしまって)困っているという書店員はどれくらいいるのでしょう? ネット全盛の時代、営業マンが持ってくるような情報は簡単にネットから手に入れることが出来るでしょうし、更に広範な情報が手に入ると思います。「書店でパソコンの前に座っている時間なんてないよ」という意見もあるでしょうけど、それこそ営業マンとの会話の時間がなくなったぶん、その時間をネットでの情報収集に使えば営業マンと話をする以上の情報を得ることができるようになったのではないでしょうか。
とまあ、書店現場に足を運んでいないと、そんな妄想というか想像が頭の中に浮かんできます。この半年、皆無とは言えないまでも、以前と比べればほとんどなくなったと言える出版社の訪問営業、その影響がどんな風に現われているのか、誰かレポートしてくれないでしょうか?