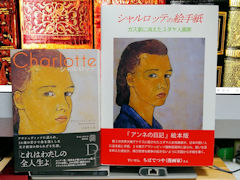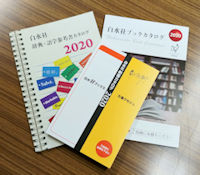いよいよ配本になったミルハウザーの新刊『ホーム・ラン
』ですが、原書のタイトルは『Voices in the Night
』で、ミルハウザーの16の短篇が収められた作品です。
原書まで追いかけている熱心なファンであれば、原書と比べて「おやっ」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか? なぜなら今回の『ホーム・ラン』には8作品しか収められていないからです。そのあたりの事情は公式サイトにも
スティーヴン・ミルハウザーの最新短篇集Voices in the Nightは、2冊に分けて刊行する。まず1冊目が、それぞれ多彩な奇想に満ちた8つの宇宙が詰まった本書『ホーム・ラン』だ。(2冊目は『夜の声』[仮題]として2021年刊行予定。)
と説明されています。「訳者あとがき」でもう少し言葉を補いますと、
(前略)本来ならその十六本を翻訳書でもそのまま一冊の本に収めればよいはずなのだが、そこで生じるのが、厚さの問題である。一般に、アメリカで出版される小説は日本より厚めである。人気作家であれば毎年二、三冊本を出すことも多い日本とは違って、アメリカでは作家が数年かけて一冊の長篇を出すだけのことも珍しくない(生活の手段は、大学で教えるなど、別のやり方で確保する)。勢い、一冊一冊は厚くなる。これは短篇集でも同じで、日本だったら二冊、三冊分あるんじゃないかと思える分量が、一冊のなかに収められていることも多い。そしてこの Voices in the Night もまさにそうで、このまま翻訳書を出すとおそらく五百ページを超える分量になる。それは日本の出版事情を考えるとさすがに少し長いのではないかと…(後略)
ということで、ミルハウザー氏に断わって二分冊にして刊行することになったのです。残りの8作品刊行まで、楽しみが増えたと思って、いましばらくお待ちくださいませ。