東京も真夏日になり、そのうち猛暑日にもなりそうな今日この頃です。全国的にも猛暑の第一波が訪れている感じがします。
猛暑の訪れと共にニュースで注意喚起されるのが熱中症です。毎年たくさんの方が病院に搬送され、少なからぬ人が亡くなっています。もしかするとコロナウイルスよりも危険なのかも知れません。
水分補給の必要性や無理な運動、昼間の外出を避けるようニュースや情報番組でも伝えられていますが、この数年変わったなとあたしが感じるのはクーラーをもっと使おうというアピールです。昼間など、自宅にクーラーがない、あるいは電気代が気になるという人には、デパートやショッピングモール、図書館などお金がかからず冷房の効いている場所に行くことが推奨されたりするくらいです。
数年前まで、テレビなどに出ているタレントや女子アナなどは、暑い夏でもクーラーを使わないことを、さもカッコよいことのようにテレビで主張していたのを鮮明に覚えています。確かに喉を使う仕事をしている人にとってクーラーで部屋を乾燥させすぎるのはよくないことでしょう。
しかし、現実にクーラーを使わないで家の中で死亡する人が跡を絶たない現実を前にして、その手の主張は完全に鳴りを潜めてしまいましたね。管見の及ぶかぎり、家ではクーラーを使いませんなどと声高に主張している人をテレビで見かけることはこの数年で全くいなくなってしまったように感じます。
さて、クーラーを適切に使うことはこの数年で十分社会に浸透したのではないかと思いますので、ここでさらにもう一歩進めてもらいたいと思うのが、テレビのアナウンサーの服装です。女性アナウンサーやキャスターはよいのですが、問題は男性アナウンサーです。彼らは頑なにスーツを脱ごうとしませんね。
深夜はともかく、昼間や夕方の情報番組などでは各地の猛暑の話題が伝えられ、外から汗ダラダラのレポーターの中継があったり、自身も熱中症のニュースを伝えているにもかかわらず、どうしてあんな暑苦しい格好をしているのでしょう。人によっては上着の下にさらにベスト(ジレ?)まで着ている人がいます。
本人はオシャレのつもりなのかも知れませんが、季節感を省みない、そしてテレビに出ていることの影響力を考慮しない行動ではないかと思うのです。仮にスタイリストのチョイスだとしたら、スタイリストとしてどうなのかと思ってしまいます。個人として夏でも上着を着ていたいというのは自由だと思いますが、テレビでに出ていることの影響力というものをもう少し考えてもよいのではないでしょうか?
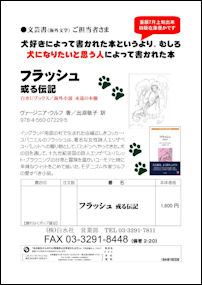 白水Uブックスの新刊『フラッシュ 或る伝記
白水Uブックスの新刊『フラッシュ 或る伝記』の重版が決まりました。

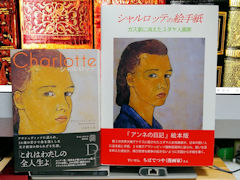
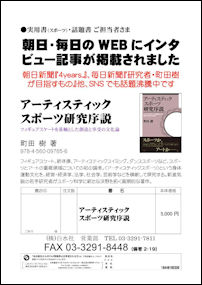




![目眩まし[新装版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=JP&ASIN=4560097631&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL160_&tag=rockfieldroom-22)

