
 流木記
流木記
ある美術館主の80年
窪島誠一郎 著
2022年5月、「無言館」は開館25周年を迎える。戦没画学生の作品を展示するこの私設美術館には毎年多くの見学者が訪れ、館長として活躍する著者の評価も高い。しかしながらここ数年、著者は二つの大きな喪失を体現した。一つは「無言館」の本家ともいえる「信濃デッサン館」を閉館したことである。このデッサン館は、著者が畏怖する村山槐多など、夭折した画家たちの作品や関係資料などを収蔵・展示してきたが、運営が困難となり、長野県立美術館に多くを売却・譲渡することとなった。もう一つは10万人に1人以下という陰茎癌と診断され、手術によってペニスを失ったことである。長年疥癬に苦しんだり、講演中に脳出血で倒れたりと、病気につきまとわれる著者にとって、これは人生を見つめ直すほどの大きな衝撃だった。この二つの大きな喪失によって、出生から現在まで、改めて半生を振り返り、自らの存在を確かめようとしたのが本書である。あえて負の部分を晒すことで、逆に傘寿を超えた著者の新たな野望すら見て取れ、不思議な共感を呼び起こす自伝的作品ともいえる。

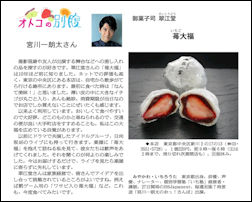


![父 水上勉[新装版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560099006&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)



