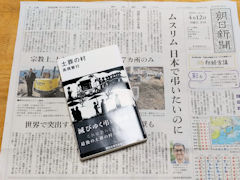長篇の『ケンジントン公園』もようやく半分ほど読み終わりました。まだ先が長いです。《エクス・リブリス》シリーズは既に次の『人類対自然』も刊行されているので早いこと読み終えないと!
長篇の『ケンジントン公園』もようやく半分ほど読み終わりました。まだ先が長いです。《エクス・リブリス》シリーズは既に次の『人類対自然』も刊行されているので早いこと読み終えないと!
そんな風に読みたい本がどんどん溜まっていく今日この頃ですが、書店でこんな本が目に留まり、ついつい買ってしまいました。『読書セラピスト』と『編集者とタブレット』です。タイトルからも想像がつくとおり、どちらも本をテーマにした作品ですよね。やはり本好きとしては気になってしまいます。
 ところで、少し前に近所の桜のトンネルを写真と共にご紹介しましたが、そちらは既に葉桜になっています。地面には桜の花びらも減り、おしべとめしべがゴミのように堆積しています。
ところで、少し前に近所の桜のトンネルを写真と共にご紹介しましたが、そちらは既に葉桜になっています。地面には桜の花びらも減り、おしべとめしべがゴミのように堆積しています。
しかし、そんな桜のトンネルの入り口付近に一本だけ時季を外して咲く桜があります。それが左の写真です。いまが盛りと咲き誇っています。
写真でわかっていただけるかなんとも言えませんが、実はこの桜は八重桜です。八重桜という明正が正しいものなのか俗称なのか、正確なところはわかりません。ただ、素人が見えてもソメイヨシノとは違うことははっきりしています。一つ一つの花がこんもりとしていて、色もソメイヨシノが白に近いのに対し、こちらはまさにピンク色です。
 それなりに交通量のある交差点に面しているので、なかなかシャッターチャンスがなかったのですが、なんとか二枚撮ってみました。ほとんど同じ構図なのはお許しください。同じ場所から撮ったものですから。
それなりに交通量のある交差点に面しているので、なかなかシャッターチャンスがなかったのですが、なんとか二枚撮ってみました。ほとんど同じ構図なのはお許しください。同じ場所から撮ったものですから。
もう少し撮影場所を変えてもよかったのですが、時間的に逆光になってしまい、桜全体も暗い感じの写真になってしまいそうだったので諦めました。
先に満開と書きましたが、根本付近には既に花びらが散っているのが見て取れます。この桜の見頃もあと数日と言ったところでしょうか。しかし、少しタイミングをずらして二種類の桜を、自宅の近所で楽しめるなんて、なかなか贅沢なことではないでしょうか。

![オーケストラの音楽史[新装版] 大作曲家が追い求めた理想の音楽](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560094322&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)