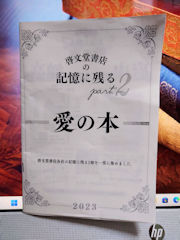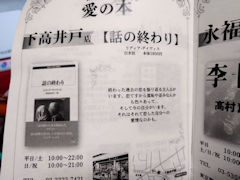この春から、数年ぶりに京王線沿線の書店も営業担当地域になったと少し前に書きました。
ということは、京王線に乗る機会が増えたということなのですが、その時にふと気づいたことがありました。
京王線は各駅停車の他に快速、急行、特急という種類があります。いろいろな掲示に、日本語表記の他に英語も書かれているのですが、それはlocal、rapid、express、special expressと表示されます。営業回りの京王線でこれを見たときにちょっと違和感を感じました。
それは「特急はspecial expressなんだ…」という違和感です。言葉を足せば「limited expressじゃないんだ」というものです。ふだん一番目にするJRでは特急は「limited express」という英語表記です。特急とは特別急行のことですから、limitedよりもspecialの方がすんなりと頭に入ってきますけど、JRがlimitedを使っているので、「それが英語らしい表記なんだ」と信じ込んでいました。
そこでちょっと気になったので、やはり営業担当地域である東横線を調べてみました。東横線も特急が走っている路線です。英語版のウェブサイトを見ますと、「limited express」とあります。やはりlimitedがスタンダードなのでしょうか。
もう一つ、やはり営業担当路線ですが、京急には他の私鉄にはない快特という種別があります。特急よりもさらに停車駅が少ない、そういう意味ではlimitedという英語が相応しいわけですが、そんな快特が走る京急の英語版路線図では「limited express」と書いてあります。
ただし、京急の場合、特急も走っていまして、それも「limited express」と表記されているのです。そして路線図をしっかり見ますと、「Limited Express(TOKKYU)」「Limited Express(KAITOKU)」と書いてあるのです。英語圏の人、これで理解してくれるのでしょうかね。ただ駅のアナウンスでは「特急」「快特」と発音されているので「TOKKYU」「KAITOKU」と添えてある方が理解の助けになるのかも知れません。
しかし、だったら快特、特急ではなく、特急、急行にしておけばよかったのではないでしょうか。なんでわざわざ快特と名付けたのでしょうか。あえて英語にするなら、快速特急のことでしょうから、「rapid limited express」ですよね。これでは長すぎますか(関西の京阪電車に「Rapid Limited Exp. RAKU RAKU」というのがあります)。
あと小田急は、急行と快速急行があり、expressとrapid expressという英語表記です。小田急の場合ロマンスカーという有料特急が別にあるので、急行・特急という種別にできず、快速急行にしたのでしょうか。
あたしの勤務先から刊行されている『鉄のカーテン(上) 東欧の壊滅1944-56』『鉄のカーテン(下) 東欧の壊滅1944-56』でした。同じ「鉄のカーテン」でも、内容はかなり異なるようです。
といったもの。東側が総崩れとなり、ベルリンの壁も崩壊するころを扱ったもののようです。それに対して『鉄のカーテン(上・下)』は



![カムイユカㇻを聞いてアイヌ語を学ぶ[新装版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=456008971X&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)