
 終わりのない日々
終わりのない日々
セバスチャン・バリー 著/木原善彦 訳
語り手は、十九世紀半ばの大飢饉に陥ったアイルランドで家族を失い、命からがらアメリカ大陸に渡ってきたトマス・マクナルティ。頼るもののない広大な国でトマスを孤独から救ったのは、同じ年頃の宿無しの少年ジョン・コールだった。美しい顔立ちに幼さの残る二人は、ミズーリ州の鉱山町にある酒場で、女装をして鉱夫たちのダンスの相手をする仕事を見つける。初めてドレスに身を包んだとき、トマスは生まれ変わったような不思議な解放感を覚える。やがて体つきが男っぽくなると、二人は食いっぱぐれのない軍隊に入り、先住民との戦いや南北戦争をともに戦っていく――。

 プーチン(下)
プーチン(下)
テロから戦争の混迷まで
フィリップ・ショート 著/山形浩生、守岡桜 訳
本書は、「世界が対峙している男」、ロシア大統領ウラジーミル・プーチンの生誕から、ウクライナ戦争に至る現在までの70年を網羅した、圧巻の伝記だ。8年がかりの調査取材によって執筆された本書は、読みやすさと充実のボリューム、高い精度の分析を兼ね備え、類書の追随を許さない。まさに「プーチンの真実」に迫る必読の書。








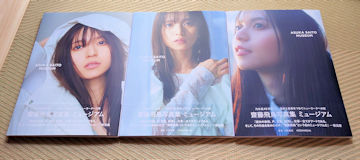
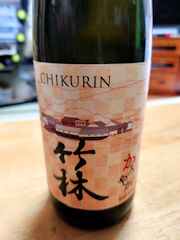


![今日からタイ語![新版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560089760&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)
![今日からはじめる台湾華語[新版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560089736&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)