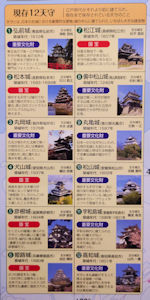奈良旅行の二日目です。昨日は郊外を中心に観光したので、今日は市街の名所を回りました。奈良駅前からバスで春日大社まで向かい、参道を本殿に向かいました。
 昨年の大河ドラマが藤原氏の全盛期を描いていたので、京都が舞台とはいえ、ここ春日大社も大勢の観光客であふれているかなと思ったのですが、朝イチだったので比較的空いていました。凛とした空気が心地よかったです。
昨年の大河ドラマが藤原氏の全盛期を描いていたので、京都が舞台とはいえ、ここ春日大社も大勢の観光客であふれているかなと思ったのですが、朝イチだったので比較的空いていました。凛とした空気が心地よかったです。
そんな春日大社や奈良公園の朝は、観光客よりも鹿の方が多いくらいでした。気付くとあちこちに鹿がいます。こちらは鹿せんべいを持っていないし、特にカバンの中に食べ物も入っていなかったので、しかもそれを察知したのか、あまり近寄ってくることはありませんでした。
 そして林の中だけでなく、参道や石畳、そこらじゅうに鹿のフンが落ちていました。きっと数え切れないほどのフンを踏んでいることでしょう。甥っ子がこれから高校受験なので、フンを踏むのも「運が付く」ということで縁起がよいのではないかと思います。
そして林の中だけでなく、参道や石畳、そこらじゅうに鹿のフンが落ちていました。きっと数え切れないほどのフンを踏んでいることでしょう。甥っ子がこれから高校受験なので、フンを踏むのも「運が付く」ということで縁起がよいのではないかと思います。
 春日大社の本殿は周囲を見て回っただけですが、藤の花の季節にはもっときれいなんだろうなあと感じました。やはり藤原氏なので藤の花なのですね。
春日大社の本殿は周囲を見て回っただけですが、藤の花の季節にはもっときれいなんだろうなあと感じました。やはり藤原氏なので藤の花なのですね。
春日大社を出て来る頃には、参拝客も増えてきました。春節の休みだからでしょう、中国からの団体客が多いようです。大型観光バスが駐車場に次々に入ってきました。
 そんな駐車場の脇を通って向かったのは二月堂です。若草山の麓というか中腹を、ずいぶんアップダウンしながら歩きました。ところどころで母の休憩タイムを挟みながらです。
そんな駐車場の脇を通って向かったのは二月堂です。若草山の麓というか中腹を、ずいぶんアップダウンしながら歩きました。ところどころで母の休憩タイムを挟みながらです。
時間はかかりましたが、なんとか辿り着いたのが法華堂、つまり三月堂です。そしてその先に二月堂がありました。高校の修学旅行では大仏殿は見ていますが、ここまでは来ていなかったので、あたしも初の訪問です。
 ここはやはり大仏殿から離れているからなのか、それほど観光客も多くはありませんでした。お水取りで有名な二月堂も、あたしのイメージはもう少し大きなものを想像していたのですが、意外とこぢんまりとした御堂でした。
ここはやはり大仏殿から離れているからなのか、それほど観光客も多くはありませんでした。お水取りで有名な二月堂も、あたしのイメージはもう少し大きなものを想像していたのですが、意外とこぢんまりとした御堂でした。
その二月堂、三月堂と向かい合うように四月堂がありました。二月と三月は知っていましたが、まさか四月もあるなんて、なんか洒落が効いていますね。まさか当時は十二か月が揃っていたなんてことはないですよね。
 そして今回の奈良旅行のメイン、母が一度は見てみたいと言っていた大仏です。このあたりまで来ると、観光客も一気に増えます。京都の有名寺社と遜色ないほどの人数です。中国人が過半を占める感じですが、韓国人も見かけましたし、欧米の方をはじめ世界各国からの観光客で賑わっています。もちろん日本人もたくさんいました。
そして今回の奈良旅行のメイン、母が一度は見てみたいと言っていた大仏です。このあたりまで来ると、観光客も一気に増えます。京都の有名寺社と遜色ないほどの人数です。中国人が過半を占める感じですが、韓国人も見かけましたし、欧米の方をはじめ世界各国からの観光客で賑わっています。もちろん日本人もたくさんいました。
 ようやく賑わっている観光地へ来たという感じを受けながら大仏殿に入りました。母は鎌倉と同じように露天に大仏さんが座っていると思っていたようで、「あの中に大仏さんがいるの?」と驚いていました。
ようやく賑わっている観光地へ来たという感じを受けながら大仏殿に入りました。母は鎌倉と同じように露天に大仏さんが座っていると思っていたようで、「あの中に大仏さんがいるの?」と驚いていました。
 大仏殿の中はもちろん混雑していました。写真を撮っても構わないので、多くの観光客が大仏を背景に記念写真を撮っていました。堂内が広いので、人の多さの割りに混み合っている感じはなかったです。
大仏殿の中はもちろん混雑していました。写真を撮っても構わないので、多くの観光客が大仏を背景に記念写真を撮っていました。堂内が広いので、人の多さの割りに混み合っている感じはなかったです。
大仏を中心に大仏殿を一回りして、外へ出ると観光客はますます増えているようです。大仏殿前の中門の外はさらに大勢の観光客です。これぞ世界遺産の観光地という感じです。
 大仏殿を出るとそのまま南下、南大門をくぐり抜けて春日大社の参道まで行き西へ向かいました。次に向かったのは興福寺です。
大仏殿を出るとそのまま南下、南大門をくぐり抜けて春日大社の参道まで行き西へ向かいました。次に向かったのは興福寺です。
興福寺に近づくと大きなビル工事のような建築現場が目に入りました。興福寺の境内のはずなのに何だろうと思って向かうと、五重塔が修繕中だったのです。ここまできて五重塔を見ることができず、ちょっと残念でした。
 五重塔の北にある東金堂を眺めつつ、中金堂を参拝。一巡りしたら北円堂を右手に眺めつつ南円堂へ。そのまま猿沢池の方へ下っていきました。
五重塔の北にある東金堂を眺めつつ、中金堂を参拝。一巡りしたら北円堂を右手に眺めつつ南円堂へ。そのまま猿沢池の方へ下っていきました。
興福寺は近鉄奈良駅からも近く、東大寺と同じくらいの賑わいでした。ただ五重塔が修繕中で、中金堂は真新しくて興醒めな感じでした。せめて国宝の阿修羅像くらいは見てくればよかったのかも知れませんが、母もだいぶ疲れているようだったので、ちょっと早いですがお昼にしようということにして興福寺を後にしました。