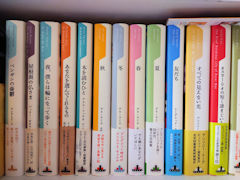この数年、沼にハマるという表現をよく見るようになりました。初出は何年くらい前なのでしょうか? 5年前には使われていましたか? 10年前にはなかった表現だと思うのですが如何でしょう?
かつて、たぶん子供のころだったと思いますが、テレビで底なし沼と言いますか、湿地帯のようなところに野生動物がはまってしまう映像を見たことがあります。もちろんドキュメンタリー映像です。はまっていたのは水牛、バッファローのような動物だったと記憶しています。
その動物がどうなったのか正確には覚えていないのですが、たぶん抜け出せずに沈んでしまったと思います。子供心に恐怖を覚えましたが、そんなあたしもはまってしまったことがあるのです。
確か小学生のころだったと思います。父方の田舎が千葉県の九十九里の方にありまして、そこへ遊びに行ったときのことです。ゴールデンウィーク頃だったのでしょうか、水だけが張ってある田んぼに誤って落ちてしまい、必死にもがいてもどんどん沈んでいくという経験をしたのです。
底なし沼と違って、田んぼには底がありますから冷静になればよかったのですが、都会育ちの子供にそんな知識や冷静さなんてあるわけがありません。あたしは必死に土手の土を手でかいて上に上がろうとしました。幸いにもなんとか抜け出せたのですが、穿いていたズボンの太もものあたりまでが泥だらけになってしまいました。そこまで沈めば、子供にとっては相当な恐怖だったことはわかっていただけるのではないでしょうか。
そんな思いを幼少のころに体験しているあたしにとって「沼にハマる」という表現をいとも喜楽に使っている昨今の風潮はとても理解できません。許しがたいとまでは言いませんが、本当に沼にハマる恐怖を知っていますかと聞きたくなります。
まあ、実際に底なし沼にハマってみろとは言いませんが、せめて『地獄の門』の一篇「悪しき導き」を一読されることをお勧めします。