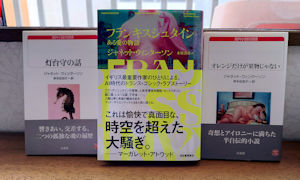乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、四期生・遠藤さくらの「さくさんぽ」第二弾が公開されました。
第一弾の散歩が都内、谷中銀座をぶらぶら散歩したわけですが、今回は石川県の山中温泉をぶらぶら散歩してきたようです。前回の谷中銀座はなんとなく街の雰囲気、空気感も伝わる散歩ロケになっていましたが、今回は果たして山中温泉に行く必要があったのか、そんな気がする散歩でしたね。
まあ、このVTRは基本的に遠藤さくらのファン、広く乃木坂46ファンがメンバーの別の一面を楽しむコンテンツですから、遠藤さくらがかわいく撮れていればそれで十分なのでしょう。さすがに金沢市内だと人も多くて、大混乱になりかねないので、比較的人の少なめな温泉地を巡ったというところではないでしょうか。たぶん本人以外にはマネージャーが一人帯同しているくらいでしょうから。
ところで、あたしはこの配信中を「数年前に山中温泉って行ったはずだよなあ」と思いながら見ていたのです。人文会の研修旅行で北陸を回ったのですが、金沢市内の書店や図書館を回った後、翌日は朝一番で永平寺に参詣する予定だったので、少しでも永平寺に近いところに泊まろうということで、山中温泉に一泊したのです。
もちろんバスでホテルに直行、そのまま宴会で就寝、翌朝も朝食を済ませたらバスで永平寺へ向かったので、泊まったホテルの名前も覚えていなければ、山中温泉がどんなところだったのかという記憶もありません。そこで当時のダイアリーを見返してみて、あたしは大きな間違いに気づきました。
さくちゃんが訪れたのは山中温泉でしたが、あたしが宿泊したのは山代温泉でした。宿泊したのも葉渡莉と明記してありました。人間の記憶ってあてにならないものですね。ただ、山中温泉と山代温泉ってそこそこ近いところにあり、もちろんどちらも石川県の温泉郷であり、福井県境に近い立地にあるという共通項があります。そして山中と山代ですから、地元の人間ではないあたしが勘違いしてもおかしくはないでしょう。
地図で見ると、山代温泉よりもさらに奥に入ったところにあるのが山中温泉で、更に進むと永平寺の方へ抜けられるみたいですが、ふつうは高速を使うでしょうから永平寺に向かうには山代温泉の方が便利なのだと思います。
また配信中でさくちゃんが「神社でご朱印をもらうんだ」と語っていましたが、彼女がもらったのは神社ではなくお寺(確か国分山医王寺)でしたよね。


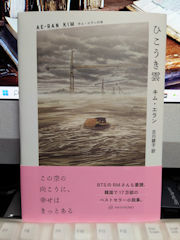



![ジョゼフ・コーネル 箱の中のユートピア[新版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560094527&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)











![[レーマン演劇論集]ポストドラマ演劇はいかに政治的か?](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4560094373&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=rockfieldroom-22&language=ja_JP)