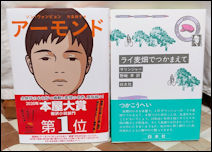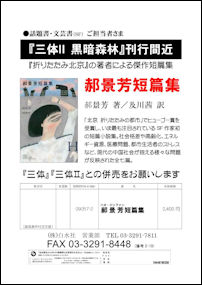わが家は戸建てですが、一階にあたしの部屋(7畳洋間)があって、そこに机やパソコンなども置いてあるのですが、その部屋は既に16本の書架が並んでいて、新たに書架を置くスペースなどどこにもない状態です。
あたしが寝ているのは二階にある、もとは納戸だった部屋(3畳)で、そこにもベッドを避けるように書架が3本、ベッド下にも小振りの書架が2本置いてあります。
仕方なく二階の廊下に薄型の書架を置いたのですが、それが右の写真というわけです。この時点でほぼ一杯になっています。ですから、この写真の奥の方、廊下を挟んだ向かいにも書架が一つ置かれているのです、写真には写っていませんが……
 そんな状態だったので、写真の手前にもう一つ書架を購入したと、昨年7月のダイアリーでご報告したわけです。それが左の写真です。
そんな状態だったので、写真の手前にもう一つ書架を購入したと、昨年7月のダイアリーでご報告したわけです。それが左の写真です。
買ったばかりなのでまだ空っぽでした。壁にはライトのスイッチがあったので、書架の裏板に穴を開け、スイッチが隠れてしまわないように工夫もしました。
昨年のダイアリーでは、この一本を買い足したことで書籍の収蔵はあと2年は持つのではないかと書きました。何か根拠があって書いたわけではありませんが、そのくらいは持ってもらわないと困ると思って、ある意味、自分の希望を書いたようなものでした。
右の写真は一枚目の写真と同じ書架です。満杯になっているのは同じです。なんとなく見えている書籍も同じものが並んでいると思います。
とはいえ、文庫や新書などが増えてくると、できるだけ同じレーベルは一緒に並べておきたいと思うのが人情ですから、並べ替えや収蔵場所移動を時々やったりしています。なので、厳密に言えば、同じ書架を移した写真ですが、並んでいる書籍に若干の異同があります。それはこの書架だけでなく、一階と二階でも移動したりしますし、一階の中、二階の中でも行ないます。
満杯までは行っていませんが、かなり埋まってしまいました。レーベルを揃えて並べるためにこちらへ移動したものもあるので、既存の書架に多少のスペースができた部分もありますので、わが家全体で考えた場合、一年も持たずにこれだけ増えたというわけではありません。
とはいえ、やはりかなりのペースで増えています。「のぎどこ」「乃木中」のBlu-rayも一緒に並んでいたりするところはご愛嬌として、空いている棚は一番下くらいしかないですね。ここが埋まるのにどれくらいの時間がかかるのでしょうか? いや、「かかる」と言うよりも、やはり「持つ」と表現したが方が実情を正確に表わせるでしょうか。
昨日、本の整理をしていて、この書架がもうここまで埋まってしまっていたことにちょっと驚きました、そんなに本を買っていたのかと。家計支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数というものがありますが、支出に占める書籍代の割合を示す言葉ってないのでしょうか? などと思ってしまう今日この頃でした。