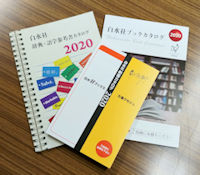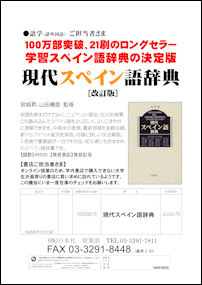東京アラート。
またしても小池百合子の大好きな横文字フレーズ。なんなんでしょう、この人?
それはともかく、今週に入って東京は格段に人が増えてきた印象を受けました。
月曜は在宅だったので、あたしの6月初出勤は昨日でした。最寄り駅までのバスも平常ダイヤに戻ったので駅までバスで行くという選択肢もありましたが、そうすると中央線は6時過ぎの電車になります。混雑具合が気になります。
ひとまず昨日はこれまでどおり徒歩で駅まで30分のお散歩。これだと5時過ぎの電車になります。両者には1時間ちょっとの時間差がありますが、これまではさすがに5時過ぎの電車は空いていました。車両によっては数人しか乗っていないところもあり、GW明けくらいはほぼ一人空きで座ることができました。
ところが昨日の同じ電車、数駅も乗ると席が埋まってきました。一人空きで座れないのを嫌って立っている人もいましたが、じきに座席はすべて埋まってしまいました。これは「密」ではないでしょうか。
もちろん、中央線の朝のラッシュからすれば「空いている」「ガラガラ」と言っていいくらいの乗車人数ではあります。しかし、多くの飲食店などで座席の間隔を空けるといった措置を施しているご時世に、電車の座席の「密」はなんとかならないものでしょうか?
5時過ぎの中央線がそんな具合ですから、コロナ以前の6時過ぎの中央線だとまず座ることは諦めないとならないでしょう。立っているのも別に構いませんが、気になるのは車内の混雑具合です。もちろんみんなマスクをして、話をしている人なんかほとんどいないので飛沫感染の可能性は少ないと思いますが……
出社後、9時前後に出社してきた同僚に聞くと、コロナ以前とまではいかないけれど、やはりかなりの混雑だったそうです。印象としては「元へ戻った」という感じになっていたそうです。
ニュースなどを見ていますと、結局、日本人ってなんだかんだ言っても在宅ワークとか新しい生活とかすぐには変われないんですよね。ほとんどの人が月金で9時から5時で働いているのでしょう。もっと時差出勤できないものでしょうか。
9時から5時と書いて、シーナ・イーストンの往年のヒット曲を思い出しました。