中四国ツアーの最終日。木曜の夕方から降り出した雨は、金曜の朝も降り続いていました。
 高松で起床し、特急に乗って徳島へ向かいます。JRの高松駅は、いわゆる櫛形ホームと言うのでしょうか、東京の人間からすると上野駅も彷彿とさせるものがあります。あたしの感覚で言えば、「ザ・終着駅」です。
高松で起床し、特急に乗って徳島へ向かいます。JRの高松駅は、いわゆる櫛形ホームと言うのでしょうか、東京の人間からすると上野駅も彷彿とさせるものがあります。あたしの感覚で言えば、「ザ・終着駅」です。
そんな高松駅の改札の内側にこんなオブジェがありました。ベンチになっていて、真ん中に座ってアンパンマンと記念撮影ができるという寸法です、撮っている人は見かけませんでしたが……
上野駅に比べれば規模も小さく、そもそも列車の発着本数が桁違いだと思いますが、こういう構造の駅は哀愁を感じさせてくれるものです。
終着駅を感じると共に、「さあ、これから旅立つぞ」という気分に浸らせてもくれます。ここから特急に乗って徳島へ向かったのです。この路線は単線ですし、電化もされていないのですね。ディーゼル特急の独特な音が響きます。四国内は予讃線、土讃線、予土線というように旧国名から命名された路線が目立ちますが、どうしてこの区間は高徳線なのでしょう。ちょっと不思議な気がします。
さて、小一時間ほどで徳島駅へ到着。雨はやみそうにありませんが、ここで仕事をこなした後は徳島空港から空路で帰京です。徳島はそれほどではありませんでしたが、東京をはじめとした各地の雨はもっと強く激しかったようで、乗る予定の飛行機の徳島到着が若干遅れ、それに伴って出発も15分ほど遅延しました。それでも無事に東京へ着陸できてよかったと思わなければなりませんね。

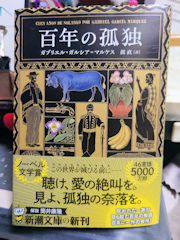
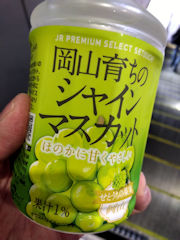


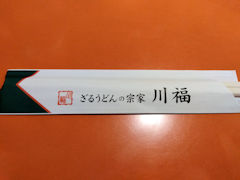










![しくみが身につく 中級ドイツ語作文[改訂版]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/148705c3.d778180b.148705c4.41f65b3d/?me_id=1213310&item_id=21291733&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9742%2F9784560099742_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=pict)