 Uブックスの『見えない人間
Uブックスの『見えない人間』は非常に面白かったのですが、いかんせん、あたしにはアメリカにおける黒人の立ち位置やその苦難の歴史に関する知識が欠如しすぎています。
漠然とアフリカから連れてこられて、白人たちの農園で酷使され、ほとんど人間扱いもされて来なかったのだろう、という程度のあやふやなものです。南北戦争で奴隷の立場はよくなったのか、相変わらずだったのか、その後の黒人の地位向上の歴史というのはどんな感じだったのか、まるでわかりません。
そんなモヤモヤした思いを抱えていましたら、タイミングよくちくま新書から『アメリカ黒人史』という一冊が刊行されました。もともとはNHKブックスで出ていたものに大幅加筆した全面改訂版だそうです。不勉強で、NHKブックスから出ていたことを知りませんでした。
それにしても、この三冊、同じ新書なので書店では一緒に並べてみることはできないものでしょうか? 新書って、どうしてもレーベルごとに配置されていて、テーマごとに並べている書店ってほとんどないですからね。でも、こんな風に並べてみるのも面白いと思うのですが。
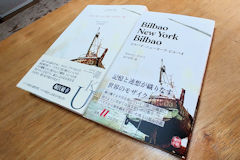
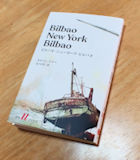


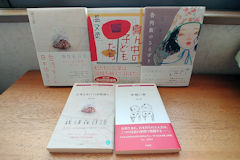








![「無伴奏チェロ組曲」を求めて[新装版]](http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=JP&ASIN=4560098263&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL160_&tag=rockfieldroom-22)

