かつて刊行されていた月刊誌『歴史読本』の編集後記だったかで、日本史では戦国か幕末を特集すれば外れない、よく売れる、というの文章を読んだことがあります。『歴史読本』ではなかったかも知れませんが、とにかく歴史系の雑誌でこんな内容のことを読んだ記憶があるのです。
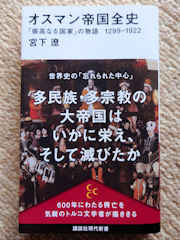 確かに、それは事実でしょうし、現在でも揺るがない人気の時代だと思います。でもこの十数年、日本史も研究が進み、特にあたしの学生時代とは比較にならないほど中世史の人気や関心が高まっていると思います。それ以外にも興味が分散し、当時ほど戦国や幕末の相対的人気は落ちているのかもしれません。
確かに、それは事実でしょうし、現在でも揺るがない人気の時代だと思います。でもこの十数年、日本史も研究が進み、特にあたしの学生時代とは比較にならないほど中世史の人気や関心が高まっていると思います。それ以外にも興味が分散し、当時ほど戦国や幕末の相対的人気は落ちているのかもしれません。
さて、では世界史ではどうでしょう。日本史に比べて範囲が広いので難しいですが、古代ギリシア・ローマ時代は人気が高いです。また日本人は考古学が好きなので、エジプトやメソポタミアなども人気だったと思います。
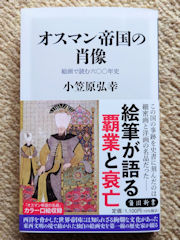 時代が下って近現代になるとドイツ史が人気と言いますか、書籍の刊行点数は多めです。フランス革命やナポレオンなども人気の時代ではないかと思います。世界史もこの十数年、いろいろな時代にスポットが当たるようになってきたと思います。
時代が下って近現代になるとドイツ史が人気と言いますか、書籍の刊行点数は多めです。フランス革命やナポレオンなども人気の時代ではないかと思います。世界史もこの十数年、いろいろな時代にスポットが当たるようになってきたと思います。
そんな世界史の中で、このところちょっと目につくのがオスマン帝国です。最近も講談社現代新書から『オスマン帝国全史』が刊行されていますし、それと前後するように角川新書でも『オスマン帝国の肖像』が刊行されています。
 少し前には中公新書でそのものズバリ、『オスマン帝国』という一冊が刊行されていますが、そのものずばりと言えば、それ以前に講談社現代新書で『オスマン帝国』が刊行されていました。
少し前には中公新書でそのものズバリ、『オスマン帝国』という一冊が刊行されていますが、そのものずばりと言えば、それ以前に講談社現代新書で『オスマン帝国』が刊行されていました。
やはりオスマン帝国と言えば数百年続いた大帝国、様々な民族、宗教、文化を包み込んだ世界帝国として、混沌とした現代でも参照できるところがあるのではないでしょうか。
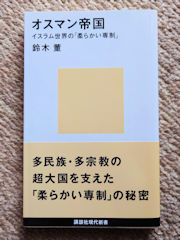 あたしが学生のころにオスマン帝国と聞けば、スルタンのハーレムくらいしかイメージできないものでしたが、それはたぶんあたしの知識があまりにも足りなかったからでしょう。そして世界史の授業ではオスマン帝国という名称よりも、オスマントルコとして習ったような記憶があります。
あたしが学生のころにオスマン帝国と聞けば、スルタンのハーレムくらいしかイメージできないものでしたが、それはたぶんあたしの知識があまりにも足りなかったからでしょう。そして世界史の授業ではオスマン帝国という名称よりも、オスマントルコとして習ったような記憶があります。
世界史では、オスマントルコ、セルジュークトルコなど紛らわしい名称がいっぱい出て来たなあ、という想い出があります。確か同じような地域で興亡したペルシアもササン朝とかアッバース朝とか、やはりややこしい帝国が次々に出て来ましたね。
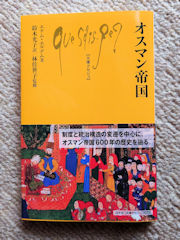 さて、そんなオスマン帝国本に新たな一冊が加わります。それが文庫クセジュの『オスマン帝国』です。文庫クセジュなので、これまで挙げた四点とは異なり、フランス人の手になる一冊です。当然、日本人著者とは視点の異なるところもあるでしょう、また一番の後発ですから、最新の研究成果、特に欧米の最新研究動向も踏まえて書かれている一冊となります。
さて、そんなオスマン帝国本に新たな一冊が加わります。それが文庫クセジュの『オスマン帝国』です。文庫クセジュなので、これまで挙げた四点とは異なり、フランス人の手になる一冊です。当然、日本人著者とは視点の異なるところもあるでしょう、また一番の後発ですから、最新の研究成果、特に欧米の最新研究動向も踏まえて書かれている一冊となります。
まもなく書店店頭に並び始めますので、いましばらくお待ちください。事前の反応も上々です。多くの注文が来ています。
なお話は戻りますが、世界史の人気で言えば、欧米よりも中国史が断トツでしょう。諸子百家や項羽と劉邦、三国志など日本人に馴染み深い時代やエピソードも多いからでしょう。この中国史も、あたしが学生のころに比べて、さまざまな時代にスポットが当たるようになってきています。書店で棚を眺めていても楽しくなります。