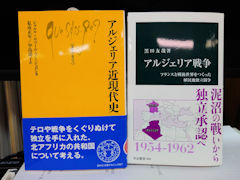今日は1月23日です。スマホなどには「一年前に取った写真」といった画像が勝手に表示されたりしますが、それを見て思い出しました。ちょうど一年前の今日、母と奈良へ行ったのでした。
 母は奈良は未踏の地で、あたしも行ったことがなかった法隆寺を見学し、柿の葉寿司を食べ、さらに唐招提寺や薬師寺を参観。翌24日は春日大社に東大寺、興福寺をのんびりと散策し、午後からは京都で買い物をして帰京しました。
母は奈良は未踏の地で、あたしも行ったことがなかった法隆寺を見学し、柿の葉寿司を食べ、さらに唐招提寺や薬師寺を参観。翌24日は春日大社に東大寺、興福寺をのんびりと散策し、午後からは京都で買い物をして帰京しました。
そんな奈良旅行からちょうど一年経ったのですね。その間、昨年の夏の終わりには、これまた母には未踏の地である北陸の金沢へと行きました。ここ数日、北陸は雪がすごいみたいですね。これから雪国は厳しいシーズンに突入なんでしょう。
しかし、その一方で春も少しずつ訪れているようで、横浜の伊勢佐木町でこんなオブジェを見かけました。有隣堂の本店を出たすぐ脇にあったものです。
 いかにも中華街のご近所だというオブジェですね。どうやら春節の飾り付けのようです。でも春節ってまだですよね。調べてみると、今年は2月17日だそうです。まだ一か月近く先ですが、もうお祭りが始まっているんですね。
いかにも中華街のご近所だというオブジェですね。どうやら春節の飾り付けのようです。でも春節ってまだですよね。調べてみると、今年は2月17日だそうです。まだ一か月近く先ですが、もうお祭りが始まっているんですね。
ところでこのオブジェ、京劇の隈取りだということはわかりますが、誰なのでしょう? 三面ありましたので三人、三役です。あたしの浅い知識だと、三国志の三英雄、劉備・関羽・張飛くらいしか思い浮かびません。
それにしても、中華街からはちょっと離れた伊勢佐木町でもこういう飾り付けが街を賑わせているわけですから、中華街はもっともっと派手な飾り付けが街中にあるのではないでしょうか。