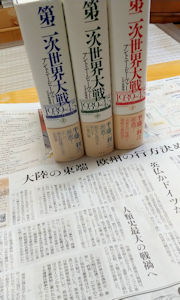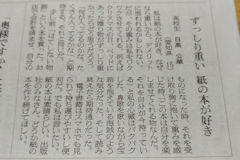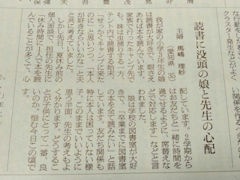盆休みも終わり、今年の夏も、暑さはともかく、気持ち的には終わりつつある、という感じがします。今年の夏はいつもとは違う、とはしょっちゅう言われていたことですが、花火大会や夏祭りが軒並み中心になったり、やっても規模縮小になっていることもずいぶんと報道されていました。
しかし、夏祭りってそんなに大事なものでしょうか? いや、農耕儀礼としての祭りは大事なものだと理解していますけど、現在のように、ただ人が集まって騒いで羽目を外すだけのような祭りにどれほどの意味があるのか、とも思います。なにせ、あたしは幼少のころからお祭りが嫌いな人間でしたので……(汗)
親戚の伯母さんが、小さいころのあたしを連れて近所のお祭りに連れて行ってくれたことがあるそうなのですが、あたしは「つまらないから早く帰ろう」と言っていたそうで、お祭り好きな伯母さんも諦めてあたしを連れて帰路に着いた、という話を後になってから聞かされました。そんな筋金入りの祭嫌いなあたしです。
しかし、世の中には都会で暮らしていても、年に一度の地元の祭りのために帰省するという人もいるんですよね。あたしには信じられないことです。まあ、今年の場合はコロナで祭りが中止でしょうし、県を跨いだ旅行は控えるように言われていますので、帰省もしなかったのかも知れませんが。
帰省と言えば、テレビのインタビューでよく聞くのは、お墓参りに行って来た、という話です。お盆って、わが家でも迎え火、送り火を焚くのでわかりますが、自宅へご先祖様を迎えるんじゃありませんか。だとしたら、空っぽのお墓に何をしに行くのでしょう? むしろ、お墓参りってお彼岸の時期にするものではないかと思うのですが、違うのでしょうか?
ちなみに、わが家は祖父の命日が1月7日(なんと、昭和天皇と同じ日)なので、1月の半ばとか、あるいは12月の早めにお墓参りをする習慣が昔からあったので、お彼岸もスルーです。もちろん、お盆にもお墓参りはしません。